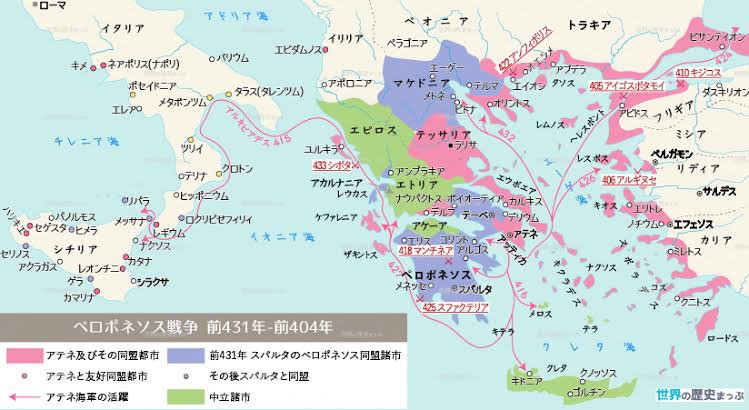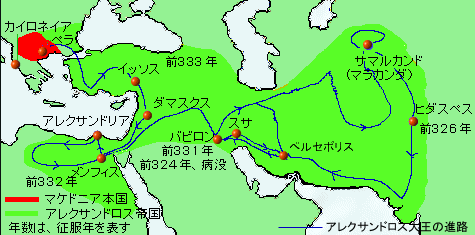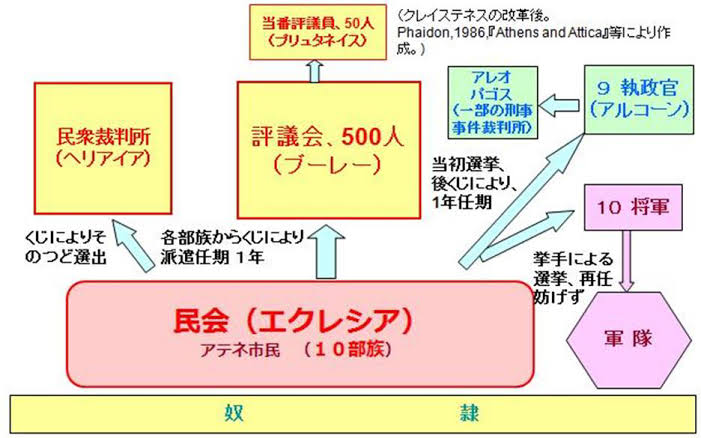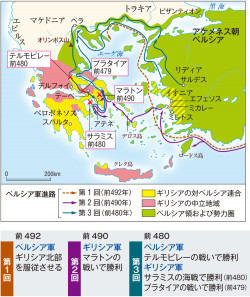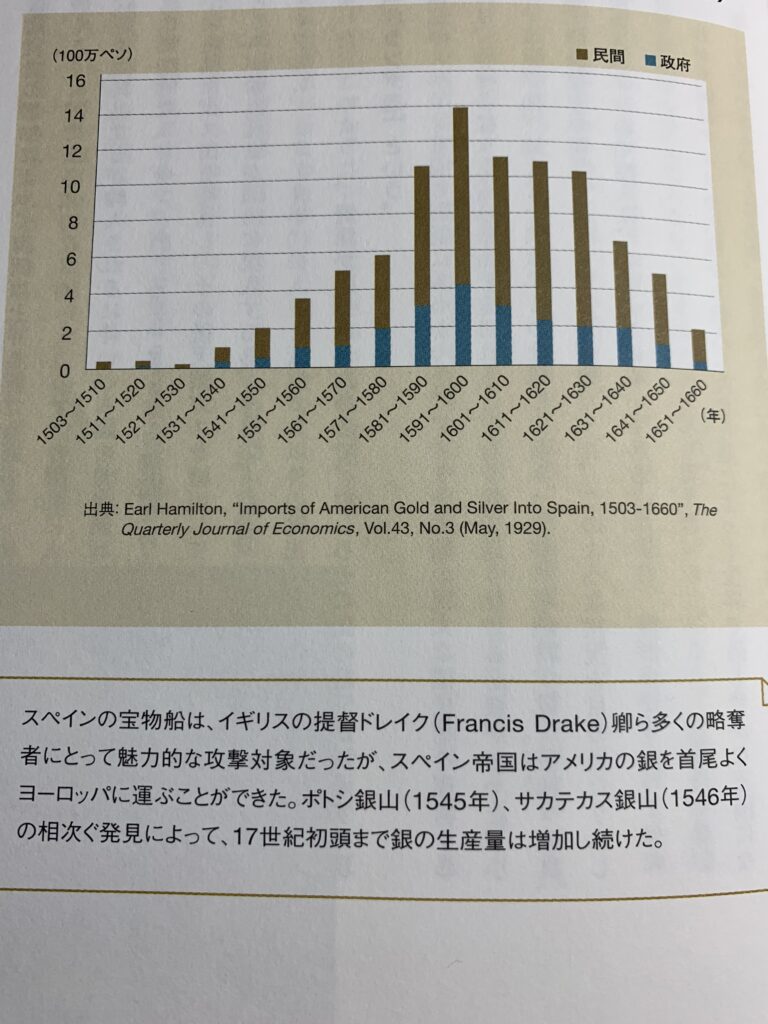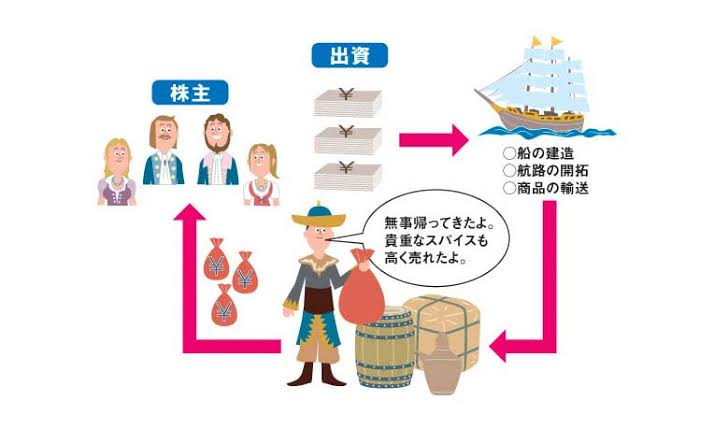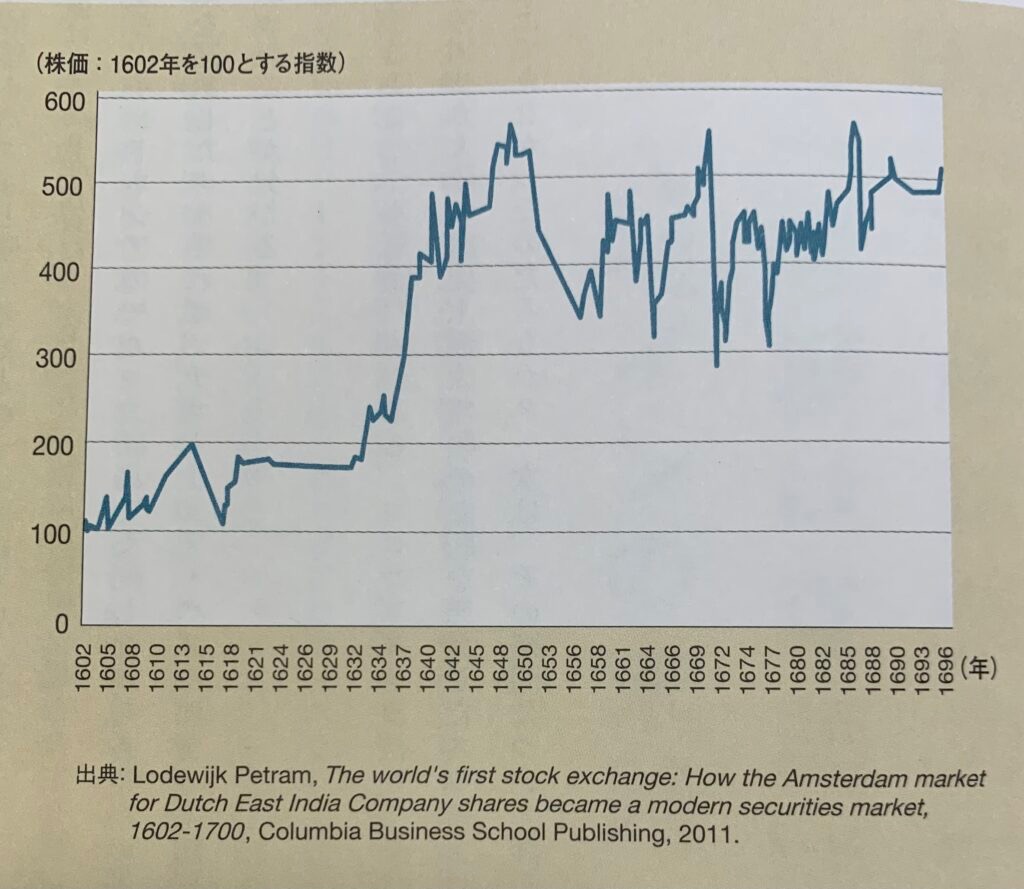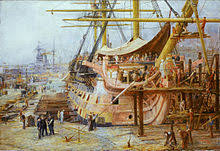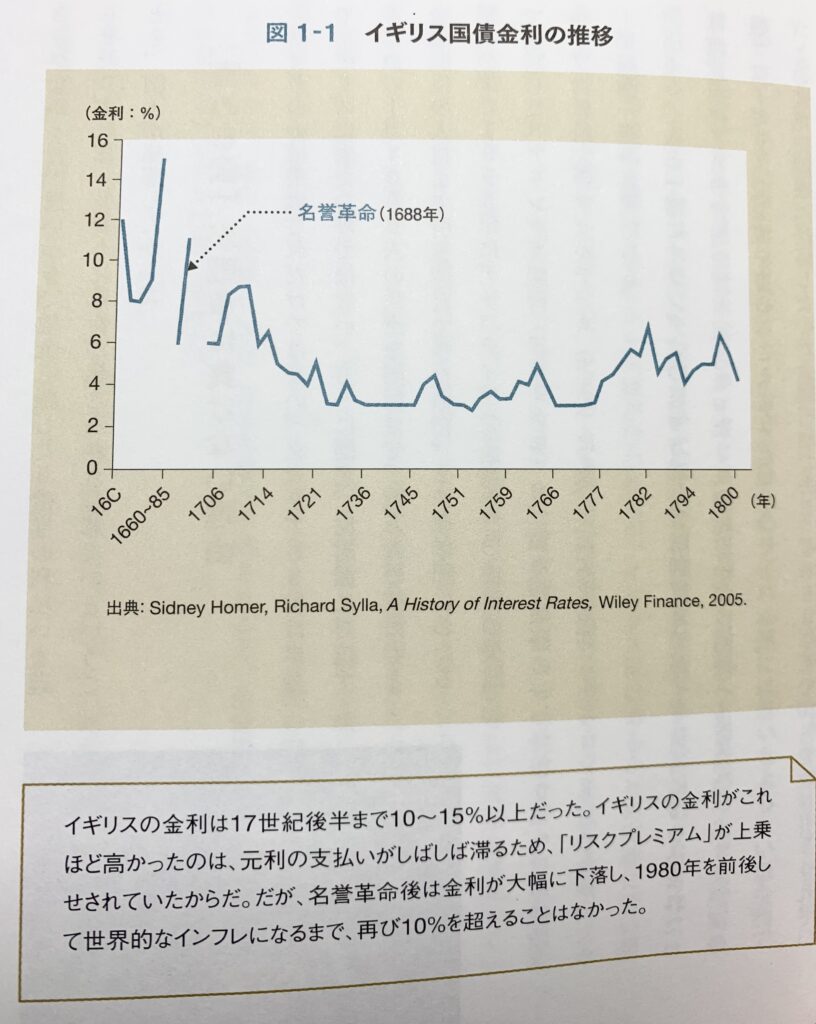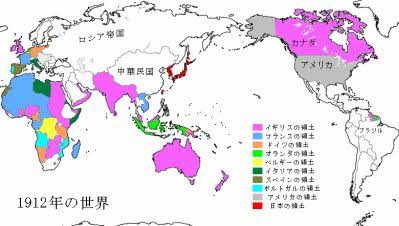BC5世紀前後、世界に数多くの考える人が登場してきました。そして今日まで残るようなさまざまな思考の原点が、草木が一斉に芽吹くように誕生しました。
この時代を、20世紀のドイツの哲学者カール・ヤスパース(1883〜1969)は「枢軸の時代」と呼びました。世界規模で“知の爆発”が生じました。
BC5世紀前後には、鉄器がほぼ世界中に普及していました。そこに地球の温暖化が始まります。鉄製の農機具と温暖な太陽の恵みを受けて、農作物の生産力が急上昇します。 その結果、余剰作物が大量に生産されて、豊かな人と貧しい人の格差が拡大しました。
財産にゆとりのできたお金持ちは、自分は働かず、使用人に農作業をやらせるようになります。
それと同時に、中国では“食客”と呼びましたが、お金持ちの家では、ある種の人々を何も仕事をさせず、食事を与えて遊ばせておくようになります。笛をたくみに吹く人や、星の動きに詳しい人、要するに現代の芸術家や学者のような人たちです。
社会全体が貧しければ、みんな農作業で手一杯です。歌う時間も夜空を見つめる余裕も生まれないし、人生について考えているひまもありません。生産力が向上し、有産階級が生まれたことで知識人や芸術家が登場してきたのです。そしてその過程で知の爆発が起こったのです。それはギリシャで始まり、ほぼ時を同じくしてインドや中国でも知が爆発しました。
哲学の祖タレスと自然哲学者が考えた「アルケー」とは
ギリシャでは、BC9世紀からBC7世紀にかけて、偉大な叙事詩人であったホメロスやヘシオドスが、ギリシャ神話を体系づけて『イリアス』や『オデュッセイア』、そして『神統記』を記しました。
それらの内容は、エーゲ文明の諸神話を融合させながら完成させたものです。こうしてギリシャ神話の世界が生まれました。
この時代の人々は、世界は神がつくったものだと固く信じていました。この時代を「ミュトスmythos(神話・伝説)の時代」と呼んでいます。
ミュトスの時代を経て、枢軸の時代に登場してきた学者たちは、まさか世界を神様がつくったはずはないだろうと考え始めます。
「何か世界の根源があるはずだ。それは何だろう」そのことをミュトスではなく、自分たちの論理で、すなわちロゴスlogos(言葉)で考え始めたのです。
そして、その「万物の根源」となるものをアルケーarcheと呼びました。ミュトスではなくロゴスによってアルケーを考えること。 そのことに最初に答えを出したといわれる哲学者がタレス(BC624頃〜BC546頃)です。
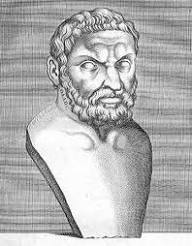
タレスはエーゲ海の東海岸(現トルコ)、イオニア地方の都市ミレトスの出身です。そのために彼につながる初期の哲学者たちを、「イオニア派」と呼びます。
また自然を探求する自然科学の立場を取っていたので、後世になると自然哲学者たちとも呼ばれました。
タレスは、この世のアルケーは何であると考えたのでしょうか。答えは水です。 今日では人間の身体の約7割が水であることも、地球上の生命の根源が水であることも判明しています。
タレスはたいへん多才な人物でしたが、エピソードもたくさん残した魅力的な人物でもありました。
あるとき、学問をいくらやっても人生の役には立たないじゃないかと、笑われたことがありました。
すると天文学に通じていたタレスは、ある年、星座の運行がオリーブの豊作を告げていることを知ると、近在の村里からオリーブの実を搾って油を採る圧搾機を、オリーブの花が咲く前に、全部買い占めてしまったのです。
そしてオリーブの実が大豊作になったとき、みんながタレスに圧搾機を借りにきたために、彼は大儲けをしました。学問がお金儲けにも役立つことを、自ら証明したわけです。
「アルケーは水だ」というタレスの学説に刺激されて、実にさまざまなアルケー論が登場してきます。
タレスの次はヘラクレイトス(BC540頃ーBC480頃)です。彼は「万物は流転する」(パンタ・レイ)という言葉を残しています。
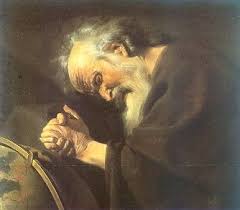
本人の言葉かどうかの確証はありませんが、プラトンがヘラクレイトスの言葉として書き残しています。
「アルケーは水だとか火だとか数字だとか言っているけれど、万物は流転するのだよ。どんどん変化していくんだよ」それがヘラクレイトスの思想でした。
もっともヘラクレイトスは、変化と闘争を万物の根源とみなし、その象徴を火としました。ここには近世になってドイツの哲学者、ヘーゲル(1770〜1831)が提唱した、正反合の弁証法の理論につながっていく発想がすでに芽生えています。
その後に、火・空気・水・土の4元素をアルケーとしたエンペドクレス(BC490頃〜BC430頃)が続きます。
彼はシチリア島のアクラガス(現在のアグリジェント)の出身です。医者であり詩人であり政治家でもありました。
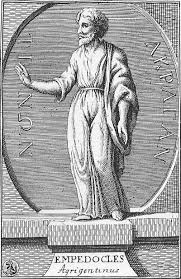
彼は4元素説を唱えました。万物の根源、アルケーは火・空気・水・土の4つであるという説です。
この4つの元素を結合させるピリア(愛)があり、分離させるネイコス(憎)があって、その働きによって4元素は集合と離散を繰り返すという理論です。
エンペドクレスは、後に述べるピュタゴラス派の影響を受けています。
この4元素については、後にアリストテレスが取り上げます。ただアリストテレスは、元素として取り上げるというよりは、4つの材料として取り上げます。
万物の根源を追求した哲学者の最後にくるのは、デモクリトス(BC460頃〜BC370頃)です。
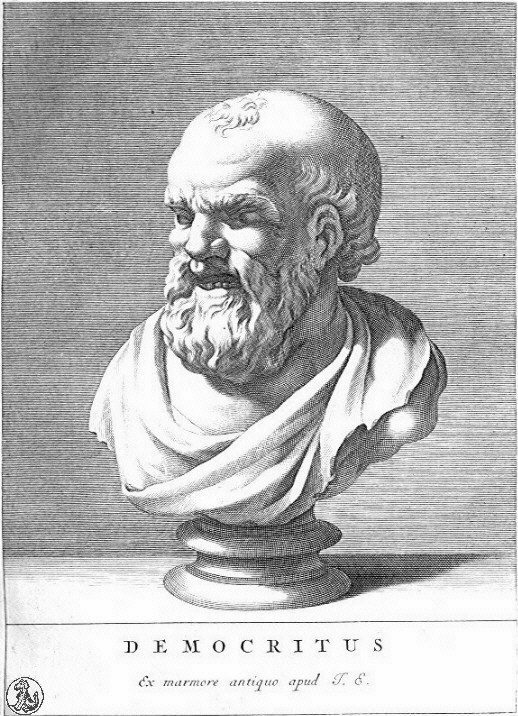
年齢からいえば、デモクリトスはソクラテス(BC469頃〜BC399)よりも、10年近く後の人物です。
彼は自然科学や倫理学、さらには数学や今日でいうところの一般教養も深く学んでいました。そしてエジプト、ペルシャ、紅海地方、さらにはインドまで、学究の旅に出ました。膨大な著作があったという記録が残されています。
デモクリトスは、アルケーはアトム(原子)であると考えました。物質を細分化していくと、これ以上分割できない最小単位の粒子(アトム)となり、そのアトムが地球や惑星や太陽を構成していると考えました。
そしてアトムによって構成された物体と物体の間の空間は、空虚(ケノン)であると考えました。すなわち真空であると。
彼は天上界を地上の世界と区別せず、そこもまた通常の物質世界であると喝破したのです。
すでに現代の唯物論に近い発想が生まれていることに驚かされます。
もう2人、自然哲学者ではありませんが、後世に大きな影響を与えた偉大な哲学者を挙げておきます。
一人は、ピュタゴラス(BC582〜BC496)です。
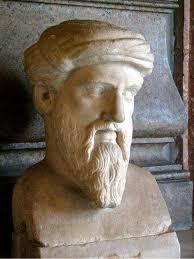
ピュタゴラスはタレスと同じくイオニア地方の出身ですが、青年期に学問のため、古代オリエントの地を遍歴しました。
諸国を遊学した後、故里に戻ってきますが、やがてイタリア半島の南部にあったギリシャの植民都市クロトーンに移住し、その地でピュタゴラス教団を創設します。クロトーンは現在のクロトーネです。
ピュタゴラスとその教団は、数学的な原理を基礎にして宇宙の原理を確立することを目指しました。
彼は万物の根源は数であると考えたのです。
ピュタゴラス教団の才能ある数学者たちは、数々の現代に残る数学の定理を発見しました。
またピュタゴラスは一絃琴を用いて、音程の法則を発見しています。そのことによって、音階を数字で表すことを可能にしました。
ところでピュタゴラス教団は、学問の集団であっただけではなく宗教的な集団でもあったようです。
彼自身が教祖のような地位に祭り上げられ、その神秘化な側面が強調されていました。
彼自身の著作物で現存するものはなく、弟子たちが書いたものや数学関係の書物の注釈によって、彼の学説や思索が残されています。
ピュタゴラスが宗教的に信じていたのは、インドの輪廻転生思想でした。その信仰のために彼は故郷のサモス島を離れて、イタリアに渡ったと考えられています。
哲学と宗教は、その誕生から発展の過程において、多くの類似点があるといわれているのですが、ピュタゴラス教団はその好例であるように思われます。
また、ピュタゴラスの死後、プラトンが輪廻転生の思想に興味を抱きました。
そしてわざわざイタリアを訪れ、ピュタゴラスの弟子であった哲学者フィロラオス(BC470頃〜BC385頃)の著作を買い求めたと伝えられています。
もう一人はパルメニデス(BC520頃〜BC450頃)です。

南イタリア(当時はマグナ・グレキアと呼ばれたギリシャの植民地)の都市エレア出身のパルメニデスは、「あるは、ある。ないは、ない」という詩を遺しました。
これは、世界は始めも終わりもない永遠不滅の一体的な存在であるという一元的な存在論です。
したがって、世界は変化や運動を被ることなく生成消滅は否定されることになります。
パルメニデスはエレア派の祖となりました。
エレア派は、感覚よりも理性に信を置いて、理性が把握する不生不滅の「有る」べき世界と人間が感覚で把握する生生流転の現実世界という二重構造を示しました。